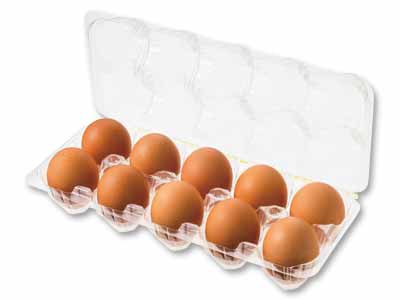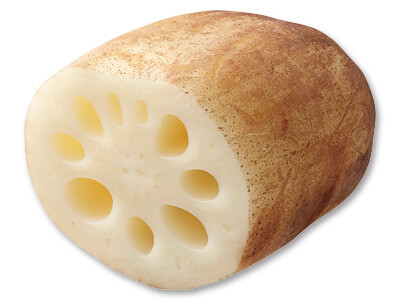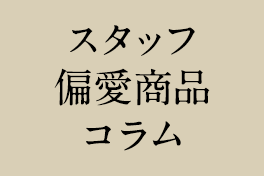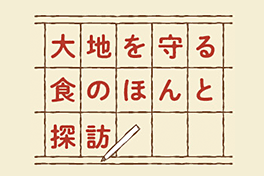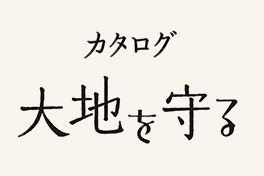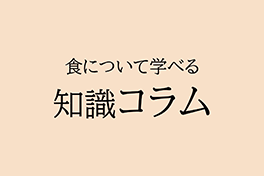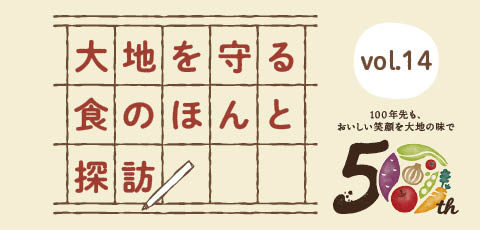
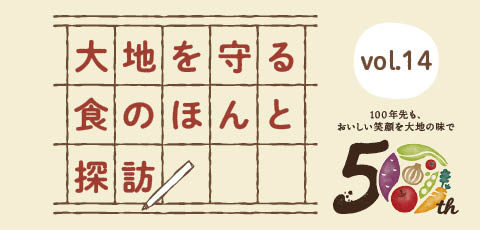
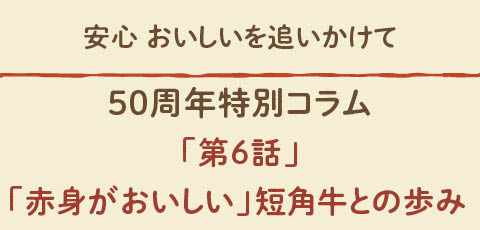
自然な環境で育てられた和牛を探していた大地を守る会と、短角牛の出合いは1970年代後半。岩手県山形村(現・久慈市山形町)とのつながりや試行錯誤があって、流通量わずか1%の「短角牛」を皆様にお届けできています。長年、大地を守る会で畜産に関わる担当者に、当時の話を伺いました。
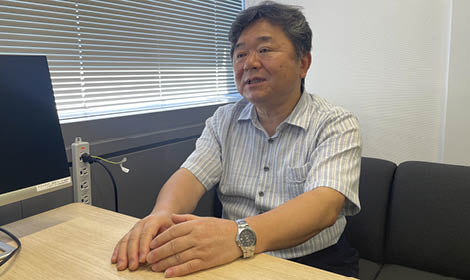
安生 三之 1983年に配送員として入社し、1985年から大地を守る会の畜産を担当。長年、精肉加工場で肉のスライスなどに関わり、牛豚肉のおいしさに精通。
牛肉本来のうまみを重視。
産地と作り上げた「プロも認める赤身肉」。
日本で健康に育ったうまみのある牛肉を探していた大地を守る会は、1970年代後半に「短角牛」と出合い、当時の岩手県山形村を紹介されました。「初期の山形村短角牛は、肉質にバラつきがありました」。初めは飼料の与え方も生産者によって異なっていた、と安生は語ります。
日本食肉格付協会が定義するランクは、霜降り肉が高く評価されます。短角牛のような赤身肉は低い評価を受けがちですが、健康に育った牛ならではの濃いうまみは食のプロからも認められるものでした。そこで、当時精肉加工場に勤めていた安生や他の畜産部門のメンバーは、肉質を改良するために動きます。東北大学の教授に歩留まりデータなどを分析してもらい、それを元にした「極力良い系統を残す」ための提案を生産者に申し入れました。

まだ産地との信頼関係を築けていない頃のこと、小規模で牛を飼っている農家が多く苦労も少なくなかったそうですが、その甲斐もあって、現在の肉質は当時と比べて安定したと言います。
国産飼料のこだわりが、
食べるときの安心に。
肉質の改良にあたって、同時に意識したのは牛に与える飼料でした。1990年代頃から小麦圧ぺん・ふすま・大豆圧ぺんなどの穀物をすべて国産でまかなう「大地スペシャル」を使用し、岩塩を除いたほぼすべての原料が国産という状態を実現しました。粗飼料のデントコーンなどは生産者が自ら作っていることが多く、輸入飼料が基本とされる国内の畜産業のなかでも、画期的な取り組みと言えます。
「牛の食べるものから、安心できる国産のものにこだわりたい」という大地を守る会の理念が反映されてきた部分です。

肥育の全期間で与える、牛たちの整腸作用に役立つ「発酵米飼料」
国産の牛肉を、
もっとおいしく、親しみやすく。
「放牧で育つ牛は、国内でも珍しい。その年に生まれた仔牛を母牛と一緒に放牧し、母乳で育てることで肉ができ上がり、翌年以降に国産飼料を与え、牛舎で肥育して出荷しています。2年目以降の牛を放牧しないのは、牧草を多く食べることで肉質のしまりがなくなり、脂身の色も変化してしまうから。試行錯誤と改良を繰り返し、おいしい赤身肉をお届けできるように努めてきました」。
日本では赤身肉の価値が昨今見直されつつありますが、まだまだ霜降り肉と比べると認知度が低い状況です。流通量1%に満たない希少な牛肉のおいしさを知って欲しいと、「お試し規格」などの取り扱いも増やしています。この機会にぜひ、歴史ある山形村短角牛を味わってください。

春に「山上げ」され、広々とした牧場で牧草と母牛の母乳で育つ山形村短角牛。