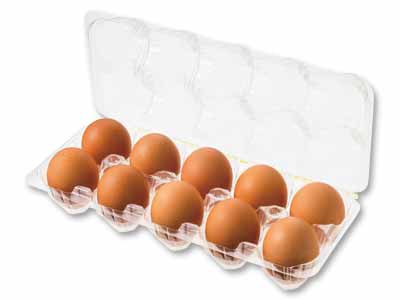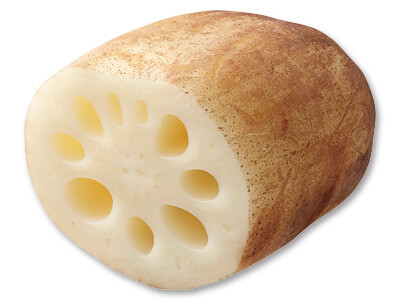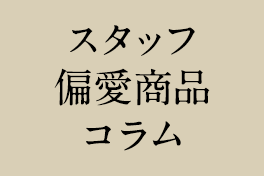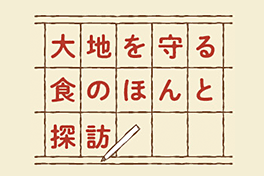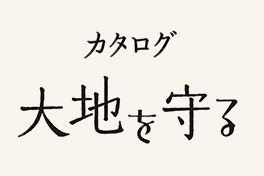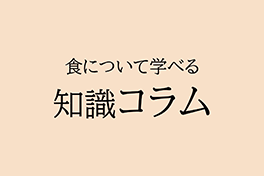大地を守る会では、伝統的な漁業を受け継ぐ近海での天然ものの魚を中心にお届けしてきました。しかし、近年日本沿岸の漁業資源量が劇的に変化しています。これまでのように、天然の水産物だけをお届けすることが困難な時代になっています。日本の水産業の現状を踏まえ、大地を守る会は今後どうあるべきか。多様な産地と長年付き合いを続けてきた、水産品担当・浅海博志に話を聞きました。(2025年130号7月7日週配布『カタログ大地を守る』掲載の情報)

浅海 博志 大地を守る会水産品担当歴33年の目利き。全国の水産生産者、産地を訪ねて回り、日本の水産業の現実を見つめ続けてきました。
日本の大衆魚は、
どれも「高級魚」に出世した。
「今年の春頃、バタバタしてたんですよ」。正月料理の定番、田作りの原料カタクチイワシの漁獲量が思わしくなく、田作りを作るのに十分な質・量のカタクチイワシが確保できるか危うくなったのです。大地を守る会の水産品を担当して33年。日本各地の産地へと足を運び続け、日本の水産業の現状をよく知る浅海は、「昔は近海でアジが獲れたら、その後1カ月は当たり前にアジが続けて獲れました。でも今は違う。今日アジが獲れても、次の日はぴたっと獲れなくなる。大衆魚と呼ばれて親しまれてきた魚の漁獲量がとにかく不安定」と嘆きます。たとえばスルメイカは、安く出回るので「おかずのかさ増し」になる魚介でしたが、ここ数年は不漁が続き、価格は高騰し、そんな呼び方は通用しません。鮭やサンマ、サバなど、かつて日本の食卓で当たり前に出てきた魚も例外ではなく、今や「高級魚」と呼んでも良いかもしれません。

記録的とされるスルメイカの不漁。イカメシや塩辛も簡単に手に入らなくなるかもしれません。
異変は10年以上前から。
天然鮭がすべて外へ出ていく
「異変を感じたのは10年以上前から。日本産の鮭がほとんど海外へ持って行かれてしまうんです。海外の方が相場が高く、日本のバイヤーは買い負けてしまう。限られたシーズン以外は、全部養殖・冷凍の銀鮭ばかり。今の日本だと、鮭は養殖の方が好まれるんです」。また、「サンマなどの水揚げ量が回復した」と前向きな報道もありましたが、生産者たちからすれば「質が落ちてしまっている」状況と言います。「脂のりの良さが特徴だった金華サバも、2年ほど前から獲れなくなりました」。自信をもってお届けできる国産魚は少なくなっているそうです。

天然漁を生業とする漁師たちは、かなり前から異変を感じていたそうです。
明日どうなるかわからない。
なら、今できる道を選ぶ。
「天然」を基本としてきた大地を守る会。資源が圧倒的に足りない現在の水産業において、天然物だけで対応することはもはや難しく、養殖や輸入に頼らざるを得ないのが本音だと言います。「この魚しか獲れなかった、このサイズしかなかった、と最近よく相談されます。考えることが必要。今できる手段で、安心しておいしく食べていただける水産品をお届けしていきたい」。大地を守る会では、規格外の魚を「もったいナイ」として売るなど、どんな魚も無駄にしない取り組みをしています。養殖についても、エコシュリンプやカキなど一部魚介類の養殖業をこれまでも許容してきました。養殖の際に与える飼料などの情報を開示し、しっかりと確認ができた生産者の魚のみを取り扱うなど、明確な基準を持って対応していきます。さまざまな模索を続ける大地を守る会の挑戦を見守っていただければと思います。

(上)小ささゆえに捨てられてしまうサバを一口大の切身にした「大地のもったいナイさばの一口切身」(下)なかなか獲れなくなった天然鮭を使った「天然紅鮭切身(うす塩味)」